attention: 黒バス 赤×黒 暗い
ユシロ名義のアカウントで掲載しているものです。(Pixiv=6661908)
以下は当時の公開内容をそのまま掲載しています。
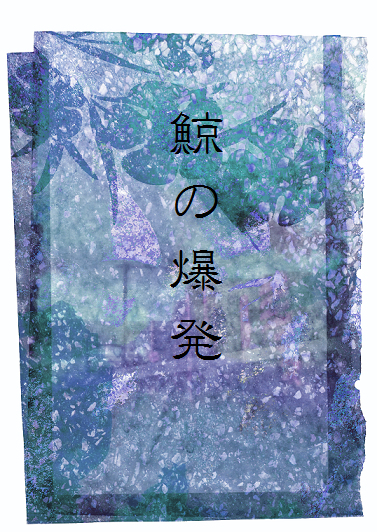
鯨の爆発
│2013 赤黒
保育園で保父として勤めるテツヤは大きくため息をついた。
思わず目を逸してしまったのも仕方ないと許して欲しい。
「やあ」
「やあ、じゃないですよ。キミも暇ですね。」
「ああ、その少ない暇を削ってでもお前に会いたかった僕が悪い。ほら、乗って。」
園児の送迎や事務作業がひととおり終わり、園の外に出たのは日も落ちかけた頃だった。
テツヤが顔を上げると見覚えのある車から見覚えのある赤い髪の男が手を振っていた。
助手席に乗り込むとおかえりと微笑んでエンジンをかける。
シートベルトを止めるのを確認すると、車はなめらかに発進した。
ドリンクホルダーに収まっているタンブラーの中身は残り少なくなっている。ずいぶん前から待機していたようだ。
「お待たせしちゃいましたね。すみません。」
「買い物のついででもある。気にするな。」
赤司が後部座席の買い物袋を指してなんとなしに言った。
夕日を避けるためにかけたサングラスの隙間から目尻の睫がしばたいたのが見えた。
きょうの夕日は随分と濃い橙色をしている。
「保育園の方は最近どうなんだ?」
「どうもなにも、忙しいのも楽しいのも、変わりありませんよ。」
「始めた当初は目の下の隈が消えないとぼやいていたくせに。」
「…それは赤司くんのせいでもあると思いますよ。」
小さく嘯くと赤司がふ、と笑った。
「時折、僕はあとどれだけテツヤを愛したらいいのかわからなくなるよ。」
「相変わらずキミの愛情表現は唐突かつ直球ですね。」
「想いはわかりやすいに越したことはないだろう?もし冗談だと流されでもしたら、僕は今貼り付けてる笑顔を保てる自信がない。」
「…貼り付けてるんですか?」
「若い女と随分楽しげに話していたな。」
「同僚に嫉妬しないでください。それに、今のところ僕は君以外に愛してると言われる筋合いはありませんよ。ボクは赤司くんのもので、キミはボクのものです。」
それを聞くなり赤司の耳がぶわっと赤く染まった。
かわいい、と思ってしまう。普段はぬけぬけとこちらの耳が痒くなるような言葉を紡いでくるくせに、その本人はちょっとした愛情を示す言葉だけでこんなにもあざやかな反応を見せてくれるのだから。黒子としてはもちろん嘘でも冗談のつもりでもないが、もっぱら彼の口をつぐませるためにそんな言葉を使うことが多い。
隣の彼はとくに表情を変えることもなく、だけど赤い耳と少し唇を尖らせた顔でハンドルをきった。
今のこの日々を幸せだと思わない方がどうかしている。
現実的な話をしてしまえば、このご時勢新卒で就職して二年。平穏無事どころかパートナーのおかげでずいぶん贅沢な暮らしをさせてもらっているのがありがたい半分自分の将来が心配な半分。いつまで彼が自分に飽きないでくれるか等不安が無いわけではない。
三年前、大学在学中の時分。思えば彼と再会したこと自体が既に奇跡だった。中学を卒業して以来高校時代も大きな大会で姿こそ見えど言葉を交わすことはほとんど無いに等しかったのだ。それが、あるとき突然赤司から着信があり、何回か他の人間も含めて食事会をしたり酒を交わすうちお互い話すことも増え、卒業後の住まい探しに赤司がルームシェアを持ちかけ、いつの間にかどちらからともなく友人から恋人の関係を委ねるという言葉にしてみればなんともあれよあれよな展開劇を経て今に至る。
その頃のことを赤司に問えば「お前のことを不快に感じた事はなかったから、改めて友好的な関係を結べるんじゃないかとふと思い立ってね。それが極まった挙句、というやつじゃないかな」となんとも曖昧な言葉を返されたが、そのあたりは黒子も流されてしまったクチなので文句は言えない。
ただ、黒子は赤司に深く心を許しているしそれが友人の分をとうに通り越していることも感じている。赤司の気持ちはわからないが、彼はもとより他人との無駄な馴れ合いを我慢できるほどおおらかな人間ではないようだし、黒子からしてみれば赤司にどう思われていようができることなら今のこの幸せのままあたたかいままいさせて欲しい。
ただ、言葉としては友人の延長でうっかり恋人になってみた、というようだが、感覚としては友人ではなくなり恋人になったという方がしっくりきそうだ。それがいつからかは忘れてしまったが確かに今黒子は赤司を愛しているという自覚がある。
幸せなのだ。とても。幸せなのに。
不確かな言語化できない渦がまた黒子の胸をチクリと刺した。
「テツヤ?」
橙色が眩しいのを言い訳に、黒子はそっと睫毛を伏せた。
そして黒子はふと思い立ったのだ。
「そういえば征十郎くん、君は鯨について詳しかったりしますか?」
「鯨?」
食卓の上を布巾で拭いていた赤司が顔を上げた。
「お昼寝の時間の前に絵本を読み聞かせするんですけど、今日は鯨のでてくる絵本を読んだんです。」
泡のついた食器を重ねて、蛇口のお湯の温度を少しずつ蛇口をずらしながら調節する。
デザインのお洒落なこの蛇口は、温度調節に少しばかりコツがいるのが難点なのだ。
IHコンロにかけてあったヤカンがグラグラ音を立て始めたので一旦手をゆすいで湯呑の準備をする。
今日の夕飯は黒子の作ったミネストローネとサラダと二種類のパスタ料理だった。
赤司はいつもどおり、おいしいと言って平らげた。
「そしたら一人の子が、“鯨は魚じゃないのになんで海にいるの?”と訊いてきたんです。テレビか何かで知ったんでしょうね。」
「テツヤはなんて答えたんだい?」
「“体が大きすぎて陸には上がれないから、海に住んでいるんだよ”と。」
「まあ間違いではないな。それに“鯨”という漢字は“計り知れない大きさの魚”という意味を込めて当てられたものらしいよ。」
「魚じゃないのに、ですか?」
「海にいるものを指して“海”や“魚”と名付けるものなんだよ。」
「そういうものですか。」
布巾をもってキッチンに入ってきた赤司に淹れたばかりのほうじ茶の湯呑を手渡す。
まだ少し薄いが、食後のお茶なのでまあいいだろう。
「でもテツヤの解いたものの方がよりロマンチックでいいね。」
「間違いではないんでしょう?」
「事実かどうかは分からない。」
ならば夢をみるのも悪くない、と赤司は笑った。
ずいぶん儚く笑うようになったな、と黒子も微笑み返した。
この頃赤司は表情を柔らかくするようになった。
それは子どもだった頃の押しつぶされるようなプレッシャーから解放され、自分をまっすぐに見つめて生きていくことを自認する今だからこそかもしれない。
二十代も後半に差し掛かって人間まだまだという年齢ではあるけれど特に、男同士での「恋人」という意識をもつ二人にとっては「愛」やら「運命」やらに頼らざるを得ない自分たちの関係にはある程度のぼやかしや妥協、いや、この場合は「ロマン」とやらが皮肉にもお似合いの言葉なのだろう。
席を立った赤司が空になった湯呑を流しに置いた。
「さて、浴槽にお湯を張ってくるよ。買い物に行ったときバスソルトの試供品を貰ったんだ。テツヤも温まるといい。」
「ボクはもう少し片付けてからもらいますから先に入ってください。」
「じゃあお先に。」
「テツヤ、お願いがあるんだけど。」
「なんでしょう?」
「読み聞かせをしてくれないか。さっき言っていた、鯨の絵本を。」
髪を乾かし、ベッドに入った黒子が首をかしげた。
「残念ながら本が手元にありません。」
「なら陸に上がれない鯨の話をしてくれないか。テツヤの思う鯨の物語を聴きたい。」
真剣、とまではいかないが、冗談で受け流すには赤司の目がやたらとまっすぐなのを見てテツヤは少し黙ったあと、カップをサイドボードに置いて、語りだした。
「…では、鯨がまだ陸にいた頃の話から…」
―――鯨はその大きな体が誰よりも嫌いだった。
周りの獣たちは小さく俊敏な体で風と共に走った。鯨にはそれがとても羨ましかった。
しかし、彼が動くと必ず誰かがあおの大きな足や尻尾に当たって怪我をした。だから彼は動かずに、一日中そこに座って空を見るばかりの彼にとってとてもつまらない(たまにおしゃべりを楽しむことだけが唯一楽しみなだけの)日々を過ごさざるえないのだった。
自分は巨大な木と同じではないか。
悪戯に呼吸し動くこともままならずただ遠く遠くを見渡して過ごす日々。
大きな体は何の役にもたたない。
あるとき、背の高いキリンは言った。
「君は喜んでその大きな影で夏の暑い日差しからみんなを休ませてくれるだろう?そんなに優しく大きな体と心の生き物を、僕は知らない」
あるとき、海を舞う大きなエイは言った。
「君はその大きな目で世界を見渡すことができる。大きな声で空を歌うことができる。大きな手で雲をなぜることができる。僕にはそれが羨ましい。」
あるとき、誰よりも早く泳ぐ鯱は言った。
「なら海にきなさいな。水はつめたいし、海は広いから誰がにぶつかって傷つけることもない。僕についておいで。」
鯨はその新しい世界に夢中になった。
体の表面を撫ぜていく潮や、なにより陸にいた頃には感じられなかった開放感。
鯨は泣いた。嬉しくて、嬉しくて。もう誰かを傷つけることもない。海の中には地上よりはるかに多くの生き物がいたし、もう苦しい思いを独りで抱え込むこともない。
呼吸を意識しなければならなくなったが、水面から顔を上げると空気が澄んで、光をとても眩しく新鮮に感じた。
鯨は幸せになった。――――
「その後鯨はどうなったんだ?」
「さあ…なにせ海は広いな大きいなですから。いくら鯨が大きいからといって、この広い地球を漂っているとなるとその後なんて皆目見当もつきません。」
「じゃあ僕がその後を話そう。鯨は海で過ごすように進化をし、そして同時に様々なものを失った。そう、例えば空気の汚れに耐えうる皮膚や、いつのまにか退化してしまった後ろ足なんかをね。もう彼は自らの意思で陸に帰ることは叶わなくなり、そしてさらに鯨は気づいてしまった。さしずめこの広い海さえも鯨を閉じ込めるだけの大きな水槽でしかなかったのだと。気づかなければよかったと、彼は後悔しただろう。そして最後に、彼は捕鯨調査の網にかけられて陸に帰ることになる。最大の生物である鯨は、増えすぎればたとえ広い海だといえど資源を食いつぶしてしまうだけの存在だからな。そうして彼の一生は終わる。めでたしめでたし。」
「めでたくはないですよ。」
「悲しい話だと言ってしまえばそれで終わってしまうが、鯨は目的を果たしたわけだ。広い世界を見ていたいという目的は世界の狭さを知ることで達成され、自らの行動に後悔し陸に帰りたいと願った上でどういう形であれ彼は陸に戻ることができた。彼は望みを二度も叶えられたのだから、幸せだと客観できるけど。」
優しい口調だがどうにも悲しい後味の物語だ。
そんなことを言ってしまえば鯨の生きる意味そのものが全てから否定されることになるではないか。
死んで初めて幸せになったなど、黒子の感覚としては幸せとは呼べない。
「どちらにせよ、子供向けではありませんね。」
うつむいてしまった黒子に、赤司は責めるでもなく淡々とした口ぶりで鯨の幸せの話を引き綴じた。
「選択するということはもう一方を捨てるということなんだよ。だが捨てたもう一方を欲張ることは自分に対しても矛盾を呼んでしまう。鯨は他にいくらでも幸せになる方法を持つことができた中、たまたまそれを選んでしまっただけさ。そもそも彼が本当は何を幸せとしていたかも他人にはわかるはずもない。…なんだか教訓めいた固い話になってしまったね。」
「キミは捨てたもう一方へ後悔したことありませんか?」
思わずそう、訊いてしまった。
うっかり「選択」という言葉に自分の思いをのせてしまった。
そう気づいて顔をあげれば、赤司の双眸が揺らいだ。
ちがうんです、と弁解しかけて、黒子は目を泳がせた。
「後悔ね…」
小さく微笑んで、呟いた。
何に、とは分からない。しかし黒子にも赤司の中にも、おそらくは同じような形の渦が巻いている。
それは不安の形をしていたり、悲しみや、たまに清々しい色さえ覗かせる。
「しろという方が酷い。」
「…すみません。忘れてください。」
そしてそれは思い出したように胸の深いところに爪を引っ掛けるのだ。
一人でいるときは刺すように痛むそれが、二人で体を寄せ合う夜はさらに涙腺のあたりに身を移してくる。
後悔という確かな形ではないかもしれない。もしくは、黒子の中の渦は「後悔」ではないのかもしれない。
だがそれは紛れもなく、赤司を愛するという言葉を被った別の暗いなにかではあるのだ。
「謝罪の言葉はいらないから、少しだけ慰めて。」
赤司が赤い髪を黒子の肩口にすり寄せた。
薄い寝巻き越しの体温が表面で混ざりあう。
シャンプーの匂いが優しすぎて、黒子は強ばった心臓を落ち着けるためにその匂いを深く吸い込んだ。
「好きです」
確かめるように小さく唇にのせてみた。
大丈夫。まだ恋人でいられる。
「殺されても大好きです」
「そんなことを可愛いことを言われたら本当に捕まえて閉じ込めてしまうだろう?」
応えるように赤司がおどけて言った。
その表情は泣きそうで、笑っていた。
甘い味がじんわりと喉の奥に広がった。
戯れるようにもう一つ紡いだ。
「ボク、赤司くんになら殺されたいです」
「ん、その時は僕もお前に殺してもらおうかな」
ぐるぐるとのたうっていた暗い渦がいつのまにか見えなくなっていた。
よかった、これで今日も安心して眠れる。
全部忘れて、いい夢だけを見て。
「おやすみなさい、赤司くん」
そう言った黒子の顔はすぐに安らかに寝息を立て始めた。
赤司は抱き寄せた腕の力を抜いてその骨ばった肩に手を添えてやった。
ねえ、言葉だけで人を殺せるなら言葉だけで人を愛すこともできるんじゃないかな。
end.
「鯨の爆発」って事件があるときき、検索してみるとホラーでも叙情詩でもなんでもなかったのですが、その響きがやたら気に入った。
深く考えすぎてお互いが見えなくなっちゃった幸せになりきれない赤黒の話。
