attention: 黒バス 赤×黒 暗い
ユシロ名義のアカウントで掲載しているものです。(Pixiv=6661908)
以下は当時の公開内容をそのまま掲載しています。
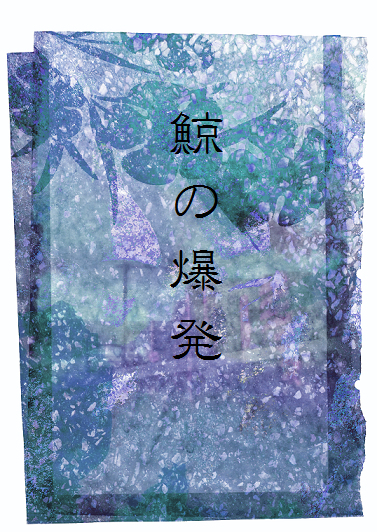
CRUEL36℃
│2013 赤黒
辛いと、彼は言った。
当然ボクは言葉の真意を聴こうと首を傾げてみたのだったが、赤い髪の彼は目を閉じたあとで、それ以上何も言葉をくれることはなかった。
些細な呟き。紡がれた言葉の意味をボクは知ることも出来ず、手にとったマグをサイドボードに置いた。
隣の彼が何を思っているのかなんて、ボクには知る由も資格もないのだろう。
【 CRUEL36℃ 】
黒子から電話があったのは3月の薄い日差しの心地よい日曜日だった。
『赤司くん、来週はお忙しいですか?』
「特別忙しいということはないが。どうした?」
『その…また将棋のご指導を受けたいなと思いまして。ええと、』
受話器の向こうの声が尻窄みに小さくなった。
僕は頬を触りながら、ごもってしまった彼の言葉を待った。
『赤司くんさえよければ、ですけど。』
「お前が会いに来てくれるなら大歓迎さ。来週日曜日なら僕は午前中出てるから、午後に来てくれるか?もしかしたら遅くなるかもしれないから、そのときはこの間の鍵で入っていてくれて構わないから」
『あ、結局鍵返してませんでしたね…。すみません返すのそのときでも大丈夫ですか?』
「ああ、なんなら持っていてくれても構わない。」
『そんなわけにはいきませんよ。ではまた来週。お願いしますね、赤司先生。』
「先生はやめろ。また来週。」
あちらの通話が切れたのを確認して、通話終了ボタンを押す。
黒子は二ヶ月に一度ほどのペースで赤司に将棋を習いに来ていた。
といっても初回からまだ三回ほどしか手を合わせていないため、専ら赤司の指すのを見て解説されながらそれをなぞるような、お世辞にも相手になるものではないのだが。
「こんにちは、お邪魔しています。赤司くん。」
「やあ。待たせたね」
昼時を少し過ぎた時間だったため、家に帰ると客間に水色髪の姿があった。
出かける前に出しておいた盤に駒を進めていたようだが行き詰まった様子からみてちょうど良い頃合いだったようだ。
買ってきた包みを台所に持って行こうと一旦ドアを閉めかけると、あ、そうだ、と黒子が立ち上がった。
「これ、良かったらもらってやってください。」
黒子が薄い紙でふんわりと包装された春色のパッケージを差し出した。受け取ってみるとどうやらハーブティーの袋のようだった。
「随分可愛らしいプレゼントだね」
「頂き物なのですが…。リラックス効果のあるお茶だそうです。僕だけでは飲みきれないのでおすそ分けです。お嫌いじゃなければですが…」
「ありがとう。だけど僕も羊羹を買ってきたんだ。嫌いじゃなければ緑茶を出してもいいだろうか?」
「あ、それは全然、や、むしろありがとうございます。いただきます。」
その時、ピロロ、と電話の呼び出しが鳴った。
「悪い。……ああ、僕だ。」
携帯電話を耳に当て首を傾げるように構える赤司にチラ、と目をやる。
昔何かのテレビで見たことがある。和服を着るときは所作も美しく無ければ格好がつかない。赤司の手つきは自然で丁寧かつ整っているものだ。
ボクも着物を着れば多少は…と思ったところでやめた。着られるのがオチだろう。
「黒子、悪いがもう少しだけ待っていてくれないか。」
「あ、それならボクはお暇します。お仕事の邪魔をするわけにはいきませんし。」
「すぐ終わる。その様子だとまた同じ手にかかったわけだろ?この僕が教授しているんだ。それだけでも解いてから帰れよ?」
「…逃がさないぞと言ったところですか。」
「そんなところだ。」
「不器用だとは思っていたけど、まさかここまでとは恐れいったよ」
「…すみません」
箸で持ち上げた味噌汁の人参は手品のおもちゃのように連なってみせた。
案の定赤司が目を離した隙に盤上は将棋とは形容し難い惨状を見せていた。
いくら始めたばかりだと言い訳したところでわざわざプロにボランティアで教えていただいている身だ。
ここに来る前にもっと本でもなんでも読んでおけばよかった…と恐縮していると「少し煮詰まりすぎた。休憩だ。」と赤司がいうものだから、時間もそれなりだったので思わず「じゃあ今日のお夕食、よければ僕がつくります!」と進言をしてしまったのだ。
黒子が作った和風きのこハンバーグと味噌汁、ほうれん草の煮浸しと卵焼きといったメニューのその日の夕食は、見た目にも赤司に新鮮な驚きを与えてくれた。
味は普通。ただ、卵焼きはちゃんと切れてないし味噌汁の具には大きさのおかしなものが入ってたり、赤司の前に用意されたものはなんとか円形をかたどっていたが彼の分のハンバーグは挽き肉に還っていた。
「た、食べられるならいいじゃないですか。」
「まあね。」
「そういえば、冷蔵庫を見たら普段も料理をされているみたいですけど、和食がお好きなんですか?」
「外食だと味の自由が利かないし、自分の食べたいものは自分でしか作れないだろう?味が濃いものや刺激味は得意じゃないから自然と和食になるのかもな。」
「なるほど。この味付けは大丈夫ですか?」
「良くも悪くも普通ってとこだね。」
「褒められてるのか貶されてるのか悩みますね。」
「僕もだ。」
なんですかそれ、と肩を落とすと赤司は少し笑って味噌汁の椀をとった。
中学を卒業して、高校で幾度か顔を合わせたことはあったが、こうして向き合って話をしたことはこれが初めてではないだろうか。
それでも不思議と黒子は、この赤司という男と話すことが楽しいとさえ思えた。
小説のネタに使いたくて赤司に将棋を教わるようになってからそろそろ半年が過ぎようとしている。
いまだ彼の本業がなんなのかは見当もつかないし(プロ棋士ではあるが彼いわく趣味の域だそうだ。わけがわからない。)赤司は面白がってはぐらかすばかりなのは癪だが、交わす言葉の端々から赤司の知識の豊かさが見える。かといってひけらかす風でもなく、黒子の話に耳を傾け頷いて、大きな受け皿でゆるりと拾っていって会話に織り込んでくれる。
なんて美しい話し方をする人なんだろう、と黒子は嬉しくなってしまうのだった。
それゆえ元同級生ながら話すのにはいささか緊張してしまう。
「もうこんな時間ですね。遅くまでお邪魔してしまって…。お皿だけ洗ったらお暇させてもらいますね。」
「…テツヤ、今夜は随分冷える。コートを持っていないようなら泊まっていかないか。将棋もみてやろう。」
「そこまでは悪いです。御夕飯までご馳走になってしまいましたし、今更言うのもなんですけどこんなヘタクソの相手ばかりさせるのは申し訳ないです。」
「テツヤが駅まで寒い思いをして帰っていくのを熱い湯を張った浴槽の中で思い浮かべてしまう方がよっぽど申し訳ない。」
「僕明日は出版社に行こうかと思っているので、ありがたいのですが…」
「なら明日の朝は僕がテツヤの家まで送っていってあげよう。よければついでに出版社まででもいいぞ。」
「ちょっと、なんでそんなに頑ななんですか君は。赤司くん、今日少しおかしいですよ?」
強引な言葉を並べる赤司に黒子が声を上げる。
「その…お誘いはありがたいですが、そこまでご迷惑をお掛けするわけには…着替えも持ってきていませんし……赤司くん?」
箸の落ちる音が響く。
赤司が泣いていた。
いや、泣くという表現は語弊があるかもしれない。
意思の強い表情と目をそのままに、つう、と滴が頬を伝い落ちた。
ぱたぱたとテーブルの上に水滴が広がる。
黒子が呆気にとられていると赤司が眉を下げて自嘲ぎみに言った。
「今夜は、一人でいたくないんだ。」
「…落ち着きましたか?」
「…悪かった」
黒子の淹れたハーブティーを受け取り、赤司は目を伏せた。
「みっともない所をみせたな」
「いえ、ただ、赤司くんも不安になることがあるんだと逆に安心しちゃいました。」
「それは馬鹿にしてるのか?」
「とんでもない。ただ漠然と絶対的な強さを感じていたものですから。」
そう言いながら黒子は失礼します、と布団をまくり赤司の隣に身を横たえた。
ベッドは広いため窮屈にはならないが、別の体温が現れたことに赤司は目を丸くした。
「保育園でお昼寝時に愚図る子には怒るより一緒に寝てあげる方が効果があるんですよ、」
「なるほど僕はその子供と同じだと。」
「似たようなものです。」
だから、と黒子が赤司の胸に手を当てて微笑んだ。
「今はゆっくり休んで、起きたらまたいつもの赤司くんに戻ればいいんですよ。」
それとも一人じゃないと眠れませんか?と問われ、首を横に振り赤司は布団を胸もとまで引っ張り上げた。
いつものあかしくん。
このあたたかい体温も、彼の向けてくれる心配そうな淡色の目も、作ってくれた夕飯の味も、このハーブティーの香りも、明日になればそっと消えてしまうのだろう。
与えられたから大事に持っていたいとか、そんな綺麗な心地ではない。
偶然にも与えられてしまったものを、また無くすのはとても────
「え?」
「…なんでもない。」
そう言って目を閉じるとあっけないほど重たい眠りに落ちていった。
翌朝、黒子は借りた寝間着を畳んで置き、ネルシャツに袖を通した。
まだ穏やかに寝息を立てる赤司の布団を整えてやり、持っていたメモをサイドボードに置いて鞄を肩に掛けた。
鍵はメモ紙に包んででポストに入れておくことにした。
「お邪魔しました。」
小さく声をかけて、黒子は扉を閉めた。
玄関のドアが閉める音を聴いてしばらく、赤司がゆっくり布団を捲り上げた。黒子がカーテンを開けたらしく大きな窓からはレースカーテン越しの柔らかい朝日が部屋を満たしてきた。
胸の中に渦巻いていたどろどろした不快感はすっきり溶け消えていた。
無論、彼がこちらの気持ちに気づこうが気づくまいが伝える方法はいくらかある。
だがそれでは駄目なのだ。
力ではなく、真っ直ぐなあの目でみてほしい。水瓶の底のような深く淡いあの色で、自分のために言葉を紡いでほしい。
いっそ声を上げて泣くことができたらどんなに楽だろうか。
昨日のあの目の色を思い出し、また心臓のあたりが酷く痛んだ。
「…辛いな」
恋というのはこんなにも痛く辛いものだったのか。
[赤司くん お疲れのようでしたけど、楽になりましたか?やはり僕は帰るとします。お夕飯ご馳走様でした。鍵はポストの中に紙に包んで入れてあるので回収お願いします。またご指導の方もお世話になりますね、先生。 黒子]
end.
黒子くんが好きなことに気づいた赤司くんと、
それに気づかない黒子くんのはなし。
